カテゴリー「歌のこととか」の記事一覧
- 2025.09.13 [PR]
- 2014.06.30 「佳いもの」聴かせてもらった×2!(Part 1 「涼風にのせて イタリアの音楽家たちとクラシックコンサートⅡ」)
- 2014.06.20 半音階進行も、やればなんとかなる!
- 2014.06.18 日本語ベラベラなのがいかんのじゃ。
- 2014.06.16 浜松で第九制覇、東京で信長制覇………出来たのか?(^◇^;)
- 2014.06.01 ブラームスに沖縄ペンタ?!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
●週末は、このブ暑い中、大イベントが4つもあった!
東京では、いつゲリラ雷雨があってもおかしくない、というぐらい、気候が波瀾万丈ですが、
静岡は、それに比べれば、
蒸し暑くて辟易しますが、
比較的安定して暑いっ!
というところ。
たまに朝晩涼しくなると、
途端にクシャミが出てきてしまうのが困るんですけどぉ、
7月12日のジョイオブ本番までは、
ゼッタイ、ゼッタイ!
風邪を引いてはならない!
ので、今日も鶏肉と生姜を煮込んで、薬膳スープで和んでおります。は~、美味しいんだ、これが。
●「涼風に乗せて」
というタイトルの、
とってもイタリア~ン♡
なコンサートが土曜日のAOIホールで開催されました。
全く「涼風」は吹いていない、蒸し暑い日だったんですけど、
イタリアからやってきた弦楽五重奏団に、アルゼンチンのアコーディオン、さらに地元静岡出身のソプラノ2人の、いわばジョイントコンサートのような演奏会。ホール内は、爽やかな音楽の風に満たされていました。
ソプラノさんお2人は、
常葉橘高校の音楽科第1期の同級生どうしで、揃って武蔵野音大に進まれ、それぞれの地元で活躍中。
このうちの1人が、私のはとこ(母親どうしがいとこ)のお姉さんで、普段は九州の宗像市にお住まい。
お2人が師事されている先生が滞伊20年に渡られるそうで、イタリア語ペラペラ。なんと、2人の弟子のために、ステージアナウンスもして下さる! 気さくな先生だぁ!
この先生のツテで、イタリアの演奏家たちを招聘して、さまざまな曲を楽しむというスタンスのシリーズ演奏会が発足し、今回がその第2回目。
前回は、どうしてもスケジュールの都合がつかず、お聴き出来なかったので、今回は満を持してAOIへゴー。
大変楽しませていただきましたぁ!
●イタリアの教授クラス揃いなんですけど!!(゚o゚;
I Solisti Veneti (ヴェネツィア合奏団)とI Filarmonici Veneti(ヴェネツィアフィルハーモニー)のメンバーズに、地元静岡出身(それも清水区! サレジオ出身だって。わあい、応援するぞ)のヴァイオリン沼野朱音(ぬまのあやね)さんがセカンドヴァイオリンで参加されての五重奏。経歴見ると、音大教授クラスしかいないヨ、イタリアの人々! どんだけ贅沢なんだ!
初っぱなから、ヴィヴァルディの「ラ・フォリア」できゃ~♡(≧▽≦)♡
特にチェロのフランチェスコ・フェッラリーニFrancesco Ferrariniさんと、コントラバスのガブリエーレ・ラギアンティGabriele Ragghiantiさんが、ものすごぉくステキ~♡
第1部最後にお2人で弾かれたロッシーニのデュエットDuettoが、かっこよかったぁ。
第2部アタマの五重奏が、これまた胸ジーン、の名曲。
プッチーニの「菊」Crisantemiというのですが、哀調を帯びた深い音色で、5人の息のピッタリ合った名演でした。
これ、プッチーニが王様の葬儀のために依頼されて作曲したものなんですって。こんな曲で送られるなんて、なんて幸せな王様なんだろう。
アコーディオン演奏は、
ピアソラを2曲。
「ブエノスアイレスの四季より」Las cuatro estaciones portenasと「リベルタンゴ」Libertango。
アコーディオンのジャンニ・ファッセッタGianni Fassettaさんは、アルゼンチン公演の際、ピアソラ夫人に絶賛された方なんだって。
リベルタンゴも大好きなんだけど、最近お気に入りの「ブエノスアイレスの~」を名手のアコーディオン+弦楽五重奏で聴けて、大・大満足!
思わずCDもゲットしてしまいましたぁ!
●おねーさんも頑張ってて、すごくステキだったのですよ!
つい久しぶりに、ものすごい弦楽を聴いてしまったので(ご招待券を頂いてしまったので、こんないいもの、タダで聴いちゃっていいのか?!って感じでアル)、楽器の話ばかりになってしまったが、
はとこのお姉さん・みどりちゃんも、ものすごぉくステキでした!
前半は、蝶々さんのような、艶やかなお着物姿でご登場。
「この道」と「赤とんぼ」の2曲でした。
「この道」の歌い出しの、
輝きと言ったら!
会場全体が、ほわぁ、と
明るい穏やかな光に満ちたよう。
にこやかな笑みを湛えたまま、美しく2曲を歌われました。はあぁ、やっぱりキレイだぁ。弦楽をバックに歌うのも、憧れるなぁ。
後半は、オレンジ系の赤いドレスで、プッチーニの「ラ・ボエーム」から「私の名はミミ」と、ロッシーニの「猫の二重唱」Duetto buffo di due gatti。
「猫の二重唱」は、ちょっと前に磐田メンバーのなかだてちゃんが、テノールの方と二重唱で楽しませて下さった大好きな曲で、ソプラノ2人のデュエットも、楽しかったぁ。表情豊かに、さまざまな猫の声(というかセリフ?)を歌い分けられていて、最後のお茶目な演技が、まだ目に焼き付いていまぁす♡
会場は、ほぼ満席で、良い席を探すのが大変でしたが、これだけの演奏家を招いてのコンサートですから、大盛況で、ホント、良かったぁ。チケット販売、あんまりお助け出来なくて、心苦しかったんですけど、いや、良かった、良かった。
どうも合唱畑の人はあまり聴きに来ていないようで、知り合いには全く会いませんでしたねー。たいてい合唱の演奏会では、山ほど知り合いに会ってしまうんだけどな。
●演奏会の感動も覚めやらぬところで
この日の夜は、ちえ蔵と光さんの美女コンビと、ジョイオブ本番打ち合わせミーティングがありました。
↑
そして、前述の会場でゲットしたアコーディオン演奏のCDを、うっかり自慢したら、さっさと自分のバッグに入れて、お持ち帰りしようとする困ったちゃんがいた!
油断も隙もないなー。
例年当日の会場設営、ステージ設営、受付からトラブルシューティングと、大汗かきながら頑張ってくれる前田の兄ぃ夫妻が、今回は2人揃ってNGだそうで、
相談の結果、なるべくフィオーレとプティポ静岡組で協力しあってやるか、ということに。
ああだこうだ、と打ち合わせて、当日プログラムと、リハーサルスケジュールを、何とか落とし込みました。
※例年みどりおねーさん(上記のはとことは別人。なんだけど、なんか「みどり」という名のおねーさんは、みんな美声でアル)とやるデュエットは、今回はO井さんがソロデビューするので、辞める予定。ちえ蔵にねじ込まれて、一瞬やってもいいかな、と心が揺れたのであるが、おねーさんと相談の結果、練習時間が少なすぎるので、却下となった。また来年かな。
まだまだ、細部を詰めていかなければならないプロジェクトですが、とりあえず大綱は出来たので、ほっ。
●で、日曜日はくみちゃんのソロを聴きに富士川へ行く、と。(以下、次号ってことで)
東京では、いつゲリラ雷雨があってもおかしくない、というぐらい、気候が波瀾万丈ですが、
静岡は、それに比べれば、
蒸し暑くて辟易しますが、
比較的安定して暑いっ!
というところ。
たまに朝晩涼しくなると、
途端にクシャミが出てきてしまうのが困るんですけどぉ、
7月12日のジョイオブ本番までは、
ゼッタイ、ゼッタイ!
風邪を引いてはならない!
ので、今日も鶏肉と生姜を煮込んで、薬膳スープで和んでおります。は~、美味しいんだ、これが。
●「涼風に乗せて」
というタイトルの、
とってもイタリア~ン♡
なコンサートが土曜日のAOIホールで開催されました。
全く「涼風」は吹いていない、蒸し暑い日だったんですけど、
イタリアからやってきた弦楽五重奏団に、アルゼンチンのアコーディオン、さらに地元静岡出身のソプラノ2人の、いわばジョイントコンサートのような演奏会。ホール内は、爽やかな音楽の風に満たされていました。
ソプラノさんお2人は、
常葉橘高校の音楽科第1期の同級生どうしで、揃って武蔵野音大に進まれ、それぞれの地元で活躍中。
このうちの1人が、私のはとこ(母親どうしがいとこ)のお姉さんで、普段は九州の宗像市にお住まい。
お2人が師事されている先生が滞伊20年に渡られるそうで、イタリア語ペラペラ。なんと、2人の弟子のために、ステージアナウンスもして下さる! 気さくな先生だぁ!
この先生のツテで、イタリアの演奏家たちを招聘して、さまざまな曲を楽しむというスタンスのシリーズ演奏会が発足し、今回がその第2回目。
前回は、どうしてもスケジュールの都合がつかず、お聴き出来なかったので、今回は満を持してAOIへゴー。
大変楽しませていただきましたぁ!
●イタリアの教授クラス揃いなんですけど!!(゚o゚;
I Solisti Veneti (ヴェネツィア合奏団)とI Filarmonici Veneti(ヴェネツィアフィルハーモニー)のメンバーズに、地元静岡出身(それも清水区! サレジオ出身だって。わあい、応援するぞ)のヴァイオリン沼野朱音(ぬまのあやね)さんがセカンドヴァイオリンで参加されての五重奏。経歴見ると、音大教授クラスしかいないヨ、イタリアの人々! どんだけ贅沢なんだ!
初っぱなから、ヴィヴァルディの「ラ・フォリア」できゃ~♡(≧▽≦)♡
特にチェロのフランチェスコ・フェッラリーニFrancesco Ferrariniさんと、コントラバスのガブリエーレ・ラギアンティGabriele Ragghiantiさんが、ものすごぉくステキ~♡
第1部最後にお2人で弾かれたロッシーニのデュエットDuettoが、かっこよかったぁ。
第2部アタマの五重奏が、これまた胸ジーン、の名曲。
プッチーニの「菊」Crisantemiというのですが、哀調を帯びた深い音色で、5人の息のピッタリ合った名演でした。
これ、プッチーニが王様の葬儀のために依頼されて作曲したものなんですって。こんな曲で送られるなんて、なんて幸せな王様なんだろう。
アコーディオン演奏は、
ピアソラを2曲。
「ブエノスアイレスの四季より」Las cuatro estaciones portenasと「リベルタンゴ」Libertango。
アコーディオンのジャンニ・ファッセッタGianni Fassettaさんは、アルゼンチン公演の際、ピアソラ夫人に絶賛された方なんだって。
リベルタンゴも大好きなんだけど、最近お気に入りの「ブエノスアイレスの~」を名手のアコーディオン+弦楽五重奏で聴けて、大・大満足!
思わずCDもゲットしてしまいましたぁ!
●おねーさんも頑張ってて、すごくステキだったのですよ!
つい久しぶりに、ものすごい弦楽を聴いてしまったので(ご招待券を頂いてしまったので、こんないいもの、タダで聴いちゃっていいのか?!って感じでアル)、楽器の話ばかりになってしまったが、
はとこのお姉さん・みどりちゃんも、ものすごぉくステキでした!
前半は、蝶々さんのような、艶やかなお着物姿でご登場。
「この道」と「赤とんぼ」の2曲でした。
「この道」の歌い出しの、
輝きと言ったら!
会場全体が、ほわぁ、と
明るい穏やかな光に満ちたよう。
にこやかな笑みを湛えたまま、美しく2曲を歌われました。はあぁ、やっぱりキレイだぁ。弦楽をバックに歌うのも、憧れるなぁ。
後半は、オレンジ系の赤いドレスで、プッチーニの「ラ・ボエーム」から「私の名はミミ」と、ロッシーニの「猫の二重唱」Duetto buffo di due gatti。
「猫の二重唱」は、ちょっと前に磐田メンバーのなかだてちゃんが、テノールの方と二重唱で楽しませて下さった大好きな曲で、ソプラノ2人のデュエットも、楽しかったぁ。表情豊かに、さまざまな猫の声(というかセリフ?)を歌い分けられていて、最後のお茶目な演技が、まだ目に焼き付いていまぁす♡
会場は、ほぼ満席で、良い席を探すのが大変でしたが、これだけの演奏家を招いてのコンサートですから、大盛況で、ホント、良かったぁ。チケット販売、あんまりお助け出来なくて、心苦しかったんですけど、いや、良かった、良かった。
どうも合唱畑の人はあまり聴きに来ていないようで、知り合いには全く会いませんでしたねー。たいてい合唱の演奏会では、山ほど知り合いに会ってしまうんだけどな。
●演奏会の感動も覚めやらぬところで
この日の夜は、ちえ蔵と光さんの美女コンビと、ジョイオブ本番打ち合わせミーティングがありました。
↑
そして、前述の会場でゲットしたアコーディオン演奏のCDを、うっかり自慢したら、さっさと自分のバッグに入れて、お持ち帰りしようとする困ったちゃんがいた!
油断も隙もないなー。
例年当日の会場設営、ステージ設営、受付からトラブルシューティングと、大汗かきながら頑張ってくれる前田の兄ぃ夫妻が、今回は2人揃ってNGだそうで、
相談の結果、なるべくフィオーレとプティポ静岡組で協力しあってやるか、ということに。
ああだこうだ、と打ち合わせて、当日プログラムと、リハーサルスケジュールを、何とか落とし込みました。
※例年みどりおねーさん(上記のはとことは別人。なんだけど、なんか「みどり」という名のおねーさんは、みんな美声でアル)とやるデュエットは、今回はO井さんがソロデビューするので、辞める予定。ちえ蔵にねじ込まれて、一瞬やってもいいかな、と心が揺れたのであるが、おねーさんと相談の結果、練習時間が少なすぎるので、却下となった。また来年かな。
まだまだ、細部を詰めていかなければならないプロジェクトですが、とりあえず大綱は出来たので、ほっ。
●で、日曜日はくみちゃんのソロを聴きに富士川へ行く、と。(以下、次号ってことで)
PR
●人間は、同時に2つのタスクをこなすのが苦手!
ちょっと前に、
人は同時に2つのことをやろうとすると、一方に集中させるためなのか、もう一方をやろうとする回路が阻害される、みたいな研究結果が発表されてました。
うん、出来ないゾ。
自信もって言えるゾ。
けど、場合によっては、
2つ同時でも、ナントカなることもあるように思う。
例えばピアノを弾く時には、
右手と左手は違うことをやってるんだし、
drummerなんか、右手と左手どころか、右足も左足も違うことをやっちゃってたりする。
だから、カンペキに不可能なわけではない。
けど、訓練なしには、
同時に2つをこなすのは難しい。
思うに、2つあるタスクのうち一方を徹底的に訓練して、それこそ目をつぶってても出来る………みたいになっていれば、
意識は自然ともう片方のタスクに集中するから、同時にこなせるようになる気がする。
弾き語りをやる人なんか、
ピアノの鍵盤はほとんど
見ていない。いわばほとんど
無意識状態で、機械のように
正確に指が動いていくから、
歌うことに集中出来るんじゃないかな。
アンジェラ・アキのパフォーマンスを見てると、そう思う。
ちなみに私は、弾き語りが下手です。指が気になっちゃって、歌に集中できません。
必死に練習して出来るようにしたのは、
Lasciar chio piangaと、
Ombra mai fuだけ。
この2曲なら、ピアノが複雑じゃないんで、ナントか脳がついていってくれるらしい。
↑
ピアノをもっと勉強しろ!
ってことか………( ̄。 ̄;)
●なんでこういう話をしているか?
と言いますと、18日にアンサンブルの練習をしていて、
林光の「うた」が、
ことのほかうまく出来たんです~(≧▽≦)
前回、半音階進行のところを、歌詞とかとっ払って、vocalizeで徹底的にスケール練習をみんなでやりまくったのですヨ。
この曲の半音階進行、
スッゴくかっこよくって、
さり気なくナポリ6度なんか
ちりばめられてて、うまく
ハマると、そりゃあもう、
カッコイい。
だけど、全員がキッチリ
このスケールをこなせないと、もたもた感が強く、
曲全体のノリがガタ落ちになってしまう。
みんな、最初はこの
半音階が苦手で、尻込みしまくっていたんですが、
尻込みしてても、スケールはなくならないんで、
この際徹底的に、そこだけ
やろう!
ってことで、だいぶ時間を割いてやりました。
●まわりくどいが、一歩一歩確実に!
音程がキッチリ入っていない状態で、歌詞をつけようとすると、音程でヘドモド、
さらに歌詞が回らなくて
目を白黒……になっちゃうことが多いように思います。
日本語の曲だと、最初っから
せっせと歌詞を付けようとする人がほとんどですが、そんなに急いでどこへ行く~(^◇^;)
日本語なんだから、あせらなくても、後でゆっくり付ければいいのになぁ、と思うんですよ、ワタクシ。
リズムやら音程やらが難しい曲の場合、オタマジャクシを追っかけるのに必死な時点で、歌詞も目で追うって、それは絶対ムリがある。
2つのタスクを無理矢理
同時にやろうとして、
脳に拒絶されてる状態、
なんじゃなかろーか?
私は、難しくて出来ないところは、まずゆっくりリズム読み(音程を入れずに、リズムだけに集中)をやります。「タタタ」とか言いながらやって、最初は、歌詞は無視。
リズムが身体に入ってきたら、次第にテンポを上げて、カンペキにリズムを染み込ませます。この、身体に覚えさせる、というのをやらないと、リズムが甘くなる。
↓
ひどくリズムが取りにくい場合は、リズム読みをしながら、リズムに合わせて手拍子を打つ。これがケッコー、最初は手が動かない。大変なんだけど、手拍子がカンペキになると、後は身体が自然とリズムを刻んでくれるので、すごく楽。
で、リズムがオッケーになったら、今度は音程の取りにくいところを確認し、スケール練習などをからめて、「ここだ!」という音の落としどころを探し出す。
リズムと音程がナントカなったところで、やっと、どっこらせ、と歌詞付けに入る。
とまあ、回りくどいみたいなんですけど、こういうやり方をします。
結局は、このように手順を踏んでやった方が、正確に出来るし、一度身体に染み込むと、もう間違わない。
多分、個々のタスクを分割して、1段階ずつ達成した方が、何でも身に付きやすいんじゃないかなぁ。
これって、子供に物を教える時と一緒ですよね。
いっぺんに、あれもこれも、と教えても、てんで身体に染み込まないんで、教える時には、一回で一個、にするのが良いんだそーです。これ、Aちゃんに教わりました。
文章でも、あれもこれも、あんなことも、こんなことも、伝えたい、と盛り込むと、どれもこれもインパクトがイマイチになり、読み手に伝わらない、と言われます。
1つの話で伝えたいことは、1つだけに絞るのが最上なんだって。
てなわけで、アンサンブルの練習の時は、私の我流の方法を、無理矢理みんなにやってもらっちゃいます。
結構キツいかも。
ごめんね!
でも、前回、これでもか、とスケール練習をした成果が、今回の練習でバッチリ出てたんですよ!
全員揃って、林光の
イジワル~な(?)
半音階進行を、楽々~と
こなしているではありませんか!
やった!
こうでなくっちゃあ!
だいたい、このアンサンブルメンバーの面々は、ともかくカンが良くて、反応が速い。
アーティキュレーションの最小単位である単語1つ1つのこなし方に気を付けて、助詞とかが飛び出さないように処理しよう、
と言った途端に、
単語1つ1つの扱い方が
ガラリ、と変わる。
そりゃあもう、
見事でした。
半音階だ、リズムだ、
ってのを、ちゃんとクリアーしているからこそ、言葉の1つ1つのニュアンスをしっかり考える余裕が出てくるんだなぁ。
曲が進むにつれて、どんどんクオリティが上がっていくのが気持ちよい。みんなの気持ちも、燃え上がってましたよね。
振っていて、至極至極、幸せでした♡
何とも言えない一体感。
みんなのおかげです。
ありがとう!
一曲終わったら、私もみんなも、汗だくでした。いやぁ、本番みたいだったねぇ。
翌日まで、みんなの歌声が頭の中でグルグル、気持ち良ぉく回ってました。
うー、早く本番、
かけたいー!
●本日のオマケ
百円ショップで見つけた
キレイな糸で、
三角ショールを編みました♡


12日間くらいかかったかな。
10玉プラスアルファくらいで編んだので、実費1,000円ちょい。
うん、それだけの値段で
12日間も楽しませてくれて、仕上がれば、また着て楽しめるんだから、編み物というのは、良い娯楽です。
一本の糸で、ずぅっと続けて編んでいくものなので、いわば長大な一筆書きのようなもの。
編んでいると、自分がせっせとハニカム構造の巣を作っているハチになったよーな気がして、そこが楽しい。
↑
ヘン?
ちょっと前に、
人は同時に2つのことをやろうとすると、一方に集中させるためなのか、もう一方をやろうとする回路が阻害される、みたいな研究結果が発表されてました。
うん、出来ないゾ。
自信もって言えるゾ。
けど、場合によっては、
2つ同時でも、ナントカなることもあるように思う。
例えばピアノを弾く時には、
右手と左手は違うことをやってるんだし、
drummerなんか、右手と左手どころか、右足も左足も違うことをやっちゃってたりする。
だから、カンペキに不可能なわけではない。
けど、訓練なしには、
同時に2つをこなすのは難しい。
思うに、2つあるタスクのうち一方を徹底的に訓練して、それこそ目をつぶってても出来る………みたいになっていれば、
意識は自然ともう片方のタスクに集中するから、同時にこなせるようになる気がする。
弾き語りをやる人なんか、
ピアノの鍵盤はほとんど
見ていない。いわばほとんど
無意識状態で、機械のように
正確に指が動いていくから、
歌うことに集中出来るんじゃないかな。
アンジェラ・アキのパフォーマンスを見てると、そう思う。
ちなみに私は、弾き語りが下手です。指が気になっちゃって、歌に集中できません。
必死に練習して出来るようにしたのは、
Lasciar chio piangaと、
Ombra mai fuだけ。
この2曲なら、ピアノが複雑じゃないんで、ナントか脳がついていってくれるらしい。
↑
ピアノをもっと勉強しろ!
ってことか………( ̄。 ̄;)
●なんでこういう話をしているか?
と言いますと、18日にアンサンブルの練習をしていて、
林光の「うた」が、
ことのほかうまく出来たんです~(≧▽≦)
前回、半音階進行のところを、歌詞とかとっ払って、vocalizeで徹底的にスケール練習をみんなでやりまくったのですヨ。
この曲の半音階進行、
スッゴくかっこよくって、
さり気なくナポリ6度なんか
ちりばめられてて、うまく
ハマると、そりゃあもう、
カッコイい。
だけど、全員がキッチリ
このスケールをこなせないと、もたもた感が強く、
曲全体のノリがガタ落ちになってしまう。
みんな、最初はこの
半音階が苦手で、尻込みしまくっていたんですが、
尻込みしてても、スケールはなくならないんで、
この際徹底的に、そこだけ
やろう!
ってことで、だいぶ時間を割いてやりました。
●まわりくどいが、一歩一歩確実に!
音程がキッチリ入っていない状態で、歌詞をつけようとすると、音程でヘドモド、
さらに歌詞が回らなくて
目を白黒……になっちゃうことが多いように思います。
日本語の曲だと、最初っから
せっせと歌詞を付けようとする人がほとんどですが、そんなに急いでどこへ行く~(^◇^;)
日本語なんだから、あせらなくても、後でゆっくり付ければいいのになぁ、と思うんですよ、ワタクシ。
リズムやら音程やらが難しい曲の場合、オタマジャクシを追っかけるのに必死な時点で、歌詞も目で追うって、それは絶対ムリがある。
2つのタスクを無理矢理
同時にやろうとして、
脳に拒絶されてる状態、
なんじゃなかろーか?
私は、難しくて出来ないところは、まずゆっくりリズム読み(音程を入れずに、リズムだけに集中)をやります。「タタタ」とか言いながらやって、最初は、歌詞は無視。
リズムが身体に入ってきたら、次第にテンポを上げて、カンペキにリズムを染み込ませます。この、身体に覚えさせる、というのをやらないと、リズムが甘くなる。
↓
ひどくリズムが取りにくい場合は、リズム読みをしながら、リズムに合わせて手拍子を打つ。これがケッコー、最初は手が動かない。大変なんだけど、手拍子がカンペキになると、後は身体が自然とリズムを刻んでくれるので、すごく楽。
で、リズムがオッケーになったら、今度は音程の取りにくいところを確認し、スケール練習などをからめて、「ここだ!」という音の落としどころを探し出す。
リズムと音程がナントカなったところで、やっと、どっこらせ、と歌詞付けに入る。
とまあ、回りくどいみたいなんですけど、こういうやり方をします。
結局は、このように手順を踏んでやった方が、正確に出来るし、一度身体に染み込むと、もう間違わない。
多分、個々のタスクを分割して、1段階ずつ達成した方が、何でも身に付きやすいんじゃないかなぁ。
これって、子供に物を教える時と一緒ですよね。
いっぺんに、あれもこれも、と教えても、てんで身体に染み込まないんで、教える時には、一回で一個、にするのが良いんだそーです。これ、Aちゃんに教わりました。
文章でも、あれもこれも、あんなことも、こんなことも、伝えたい、と盛り込むと、どれもこれもインパクトがイマイチになり、読み手に伝わらない、と言われます。
1つの話で伝えたいことは、1つだけに絞るのが最上なんだって。
てなわけで、アンサンブルの練習の時は、私の我流の方法を、無理矢理みんなにやってもらっちゃいます。
結構キツいかも。
ごめんね!
でも、前回、これでもか、とスケール練習をした成果が、今回の練習でバッチリ出てたんですよ!
全員揃って、林光の
イジワル~な(?)
半音階進行を、楽々~と
こなしているではありませんか!
やった!
こうでなくっちゃあ!
だいたい、このアンサンブルメンバーの面々は、ともかくカンが良くて、反応が速い。
アーティキュレーションの最小単位である単語1つ1つのこなし方に気を付けて、助詞とかが飛び出さないように処理しよう、
と言った途端に、
単語1つ1つの扱い方が
ガラリ、と変わる。
そりゃあもう、
見事でした。
半音階だ、リズムだ、
ってのを、ちゃんとクリアーしているからこそ、言葉の1つ1つのニュアンスをしっかり考える余裕が出てくるんだなぁ。
曲が進むにつれて、どんどんクオリティが上がっていくのが気持ちよい。みんなの気持ちも、燃え上がってましたよね。
振っていて、至極至極、幸せでした♡
何とも言えない一体感。
みんなのおかげです。
ありがとう!
一曲終わったら、私もみんなも、汗だくでした。いやぁ、本番みたいだったねぇ。
翌日まで、みんなの歌声が頭の中でグルグル、気持ち良ぉく回ってました。
うー、早く本番、
かけたいー!
●本日のオマケ
百円ショップで見つけた
キレイな糸で、
三角ショールを編みました♡
12日間くらいかかったかな。
10玉プラスアルファくらいで編んだので、実費1,000円ちょい。
うん、それだけの値段で
12日間も楽しませてくれて、仕上がれば、また着て楽しめるんだから、編み物というのは、良い娯楽です。
一本の糸で、ずぅっと続けて編んでいくものなので、いわば長大な一筆書きのようなもの。
編んでいると、自分がせっせとハニカム構造の巣を作っているハチになったよーな気がして、そこが楽しい。
↑
ヘン?
●という話を、マエストロが話して下さるんですが。
クラシックの合唱なんてやってると、実に、実に
日本語はクセモノの言語である、と頭を抱えてしまうものなんであります。
母国語だから、意味も
わかりやすいし、
訴求力が高いし、
歌いやすいんじゃないの~?
と思われるでしょうけど、
西洋音楽の曲の中で、
音としての響きの美しさを
出そう、とあがいていると、
実は日本語特有の
発音構造がもんのすごく
邪魔だったりするんです。
西洋の言葉の発音の場合、
まず子音が先に立って、
その後に母音が続いてくる、
という場合がほとんどです。
ところが日本語の場合は、
あいうえお以外は、全て子音と母音が渾然一体となった音で発声される。これが、実は難しいのです。
●母音だけ聞こえてれば、後はどうとでもなる! と普段教えられている(^◇^;)
歌う場合、どこできれいな
響きが出るか?
というと、子音ではなくて、
母音のところ。
簡単に言うと、
子音で地ならししたところに、母音という発生器を
据え付けて、そこで初めて
1音ずつがきれいな音になって響くわけです。
例えば『ウエストサイドストーリー』の「トゥナイト」で見てみると、
Tonightのtoとnightに音符が
割り振られています。
母音のところを、ひらがな表記にしますと、
Tぅ nあいt
です。
この「ぅ」と「あい」の
響きが美しく聞こえないと、
実は全く曲にならない。
子音も鳴らさなきゃ、と
ガンバると、それしか聞こえなくて、肝心の母音の響きがなくなっちゃって、結果的に、美しい響きが前に飛ばない。前に飛ばないってことは、要するに、聴いてる側にキレイに聞こえないってこと。
んなもんだから、うちの
マエストロいわく、
「言葉なんて、実はどうでもいいんですよ。母音で響かせることの方が大事です。言葉は、つけられる人がつけておけばいいんで、つかないところは、母音だけでつなげてやってごらんなさい。意外とちゃんと聞こえてしまうものなんですよ」
だそうです。
ほんまかいな?!
と思ったんですが、ライブの時、試しに高くて大変なところを母音だけでやってみました。そしたら、ちゃんと言葉としてお客さんは聴いていたらしい……です! 後で聴きに来てくれた友人に確かめました。
うーむ、脳が補完してくれてもいるらしい。便利。
↑
※磐田バッハのマタイ全曲演奏会前の強化合宿では、みんなまだ言葉が回ってなくて、そりゃもう、真っ青!(2月本番の1月合宿なのにぃ!)で、口々に「いいんだよ、母音でつなげていけば! うん、きっと、誰かが言葉を言ってくれるよ!(って、誰が~!)」と慰めあったのでした………。
先日のソーニョ練習の時も、こっそり母音唱法でやってたんですが。
MiskinisのAve Mariaの真ん中あたり(16~17小節)で、ソプラノが
E-Fis(F♯)-Gis(G♯)-Fis(F♯)
Je-su, Je-su
とやるとこがあるんですが、
これ、子音のj-s j-sを
一生懸命やろうとすると、
なんか、悲鳴状態になっちゃうんですよー(ToT)音程も高くて半音階だし。
キリストのことなんで、
一番大事な歌詞でもあるんですけど、
一番大事な歌詞の、
一番の聞かせどころが
絶叫系悲鳴じゃ、台無しですよね………( ̄。 ̄;)
で、言葉の発音は、もう
他のパートにおまかせして、
私は[e]-[u], [e]-[u]でやっちゃいました。
結果、その方が
安定した響きになったように思います。
●西洋語に比べて日本語の何が難しいか?
という話に戻りますが、
子音と母音がくっついちゃうのが普通、の言葉である上に、現代語の発音は、結構響きが浅い……というか、口先でチャキチャキ話している。
マエストロが以前、信時潔の曲をイタリアに持っていく前に、(曲の中身が非常に能狂言の世界的なので)能狂言の先生の教えを乞われたことがありまして。
その時のお話では、日本語の発音発声は、室町時代以前と以後くらいで大きな変化があったのではないか、との事。(そう言えば、英語にも大母音推移、とかいうのがあったらしい。昔の英語発音は、今のものとは、てんで違って聞こえるらしいです)
平安から室町くらいは、
端的に言えば、能狂言で使われているような、口腔の奥の方で響かせる感じの発声をしていたらしいです。
それが、江戸に入ってからは、いわゆる江戸っ子言葉の
「江戸っ子だってねぇ、寿司食いねぇ」的なアップテンポで、口腔の比較的前の方で発音する発声に変わっていったんですって。
政治の中心が関西から関東へ移っていった、というのも関係してるのかなぁ。
で、ともかく、現代語になると、ほとんど口腔の奥の方で発音することは日常的にありません。キビキビした感じで良いのですが、そうなると、母音のうちでも「イ」とか「エ」は、唇を左右に引いて、ちょっと平べったいサウンドを使って表現するようになった。
これが、歌う時、大きな障害! 男声ではあまり感じないんですが、女声では、「イ」と「エ」が出てきた瞬間に、現代日本語発音の平べったい音になりやすい。
女性の方が日常的に
「えーっ!」とか、
「いいー!」とか、
叫ぶからだろうか。
※そー言えば、「あ」も難しい。
東日本復興ソングの「花はさく」の聞かせどころの「はな~は は~なは はなはさく」の「な」だけ、なんか平べったくベトーっとした音が鳴っちゃって台無しになりやすい。音形のせいかしらん。ドイツの少年合唱団と一緒に歌った時、彼らはha-na-wa ha-na-wa ha-na-wa-sa-kuで発音してて、そりゃあきれいな「な」でございました。ちゃんとNの口をしてから、Aの母音に入るので、美しいのだなー。
室町くらいの深い響きの母音は、どーいう感じか?
というと、野村萬斎さんのセリフ回しを思い出していただけばよい。
「これはこのあたりの者でござる。やいやい、太郎冠者、あるか」みたいなヤツです。
南京玉すだれの口上とかも、いいかもしんない~(≧▽≦)
能狂言の、口腔の深いところで響かせる倍音は、実はドイツリート的なのかもしれませんねー。
というわけで、
現代日本語の達人である
現代人の私たちは、
つい日常の言語感覚で
日本語の曲を歌ってしまい、
ドツボにハマるのであります。
現代語発音も、うまく使えば、いい感じ~(≧▽≦)で使えるところもたくさんあるので、最近マエストロは、従来の基本音型3つの使い分けに、この古語風(リアrear)と現代風(フロントfront)も加えてチェンジするように指導されてます。ほとんど車のシフトチェンジ状態~(≧▽≦)。
※この間なんか、廣瀬量平の『海鳥の詩』で「ゆくえ」というのを古語風に、
「ゆくゑ」(発音はiyu-ku-weで、ご丁寧にもkは撥音ではなく、鼻濁音的)で考えるといい、と教えて下さり、なるほど、その方がここではハマる! と喜んでメモしてしまった。
だいたいにおいて、譜面に、コレコレのことを(自分に分かる形でいいんですが)書いておけ、という指示がたくさん入ります。特有の用語がたくさんあって、それをきっちり書いておかないと、置いてかれてしまう。
みんなの共通認識で、用語を決めておくと、効率的に短時間で曲が整う、というのがマエストロの持論なんでありますが、確かにこの方法、便利なんです。
基本音型3つについては、また改めて書いてみたいと思いますが、フロントだ、リアだ、と一言譜面に書いておくだけで、要求される音に入ろう、という態勢が出来ますから、ラクチンです。
「出来る、出来ないは別として、まずやろうとすることが大事なんです」
↑
出来ない群れである私たちを、叱咤激励して下さるマエストロの口癖でござる。
クラシックの合唱なんてやってると、実に、実に
日本語はクセモノの言語である、と頭を抱えてしまうものなんであります。
母国語だから、意味も
わかりやすいし、
訴求力が高いし、
歌いやすいんじゃないの~?
と思われるでしょうけど、
西洋音楽の曲の中で、
音としての響きの美しさを
出そう、とあがいていると、
実は日本語特有の
発音構造がもんのすごく
邪魔だったりするんです。
西洋の言葉の発音の場合、
まず子音が先に立って、
その後に母音が続いてくる、
という場合がほとんどです。
ところが日本語の場合は、
あいうえお以外は、全て子音と母音が渾然一体となった音で発声される。これが、実は難しいのです。
●母音だけ聞こえてれば、後はどうとでもなる! と普段教えられている(^◇^;)
歌う場合、どこできれいな
響きが出るか?
というと、子音ではなくて、
母音のところ。
簡単に言うと、
子音で地ならししたところに、母音という発生器を
据え付けて、そこで初めて
1音ずつがきれいな音になって響くわけです。
例えば『ウエストサイドストーリー』の「トゥナイト」で見てみると、
Tonightのtoとnightに音符が
割り振られています。
母音のところを、ひらがな表記にしますと、
Tぅ nあいt
です。
この「ぅ」と「あい」の
響きが美しく聞こえないと、
実は全く曲にならない。
子音も鳴らさなきゃ、と
ガンバると、それしか聞こえなくて、肝心の母音の響きがなくなっちゃって、結果的に、美しい響きが前に飛ばない。前に飛ばないってことは、要するに、聴いてる側にキレイに聞こえないってこと。
んなもんだから、うちの
マエストロいわく、
「言葉なんて、実はどうでもいいんですよ。母音で響かせることの方が大事です。言葉は、つけられる人がつけておけばいいんで、つかないところは、母音だけでつなげてやってごらんなさい。意外とちゃんと聞こえてしまうものなんですよ」
だそうです。
ほんまかいな?!
と思ったんですが、ライブの時、試しに高くて大変なところを母音だけでやってみました。そしたら、ちゃんと言葉としてお客さんは聴いていたらしい……です! 後で聴きに来てくれた友人に確かめました。
うーむ、脳が補完してくれてもいるらしい。便利。
↑
※磐田バッハのマタイ全曲演奏会前の強化合宿では、みんなまだ言葉が回ってなくて、そりゃもう、真っ青!(2月本番の1月合宿なのにぃ!)で、口々に「いいんだよ、母音でつなげていけば! うん、きっと、誰かが言葉を言ってくれるよ!(って、誰が~!)」と慰めあったのでした………。
先日のソーニョ練習の時も、こっそり母音唱法でやってたんですが。
MiskinisのAve Mariaの真ん中あたり(16~17小節)で、ソプラノが
E-Fis(F♯)-Gis(G♯)-Fis(F♯)
Je-su, Je-su
とやるとこがあるんですが、
これ、子音のj-s j-sを
一生懸命やろうとすると、
なんか、悲鳴状態になっちゃうんですよー(ToT)音程も高くて半音階だし。
キリストのことなんで、
一番大事な歌詞でもあるんですけど、
一番大事な歌詞の、
一番の聞かせどころが
絶叫系悲鳴じゃ、台無しですよね………( ̄。 ̄;)
で、言葉の発音は、もう
他のパートにおまかせして、
私は[e]-[u], [e]-[u]でやっちゃいました。
結果、その方が
安定した響きになったように思います。
●西洋語に比べて日本語の何が難しいか?
という話に戻りますが、
子音と母音がくっついちゃうのが普通、の言葉である上に、現代語の発音は、結構響きが浅い……というか、口先でチャキチャキ話している。
マエストロが以前、信時潔の曲をイタリアに持っていく前に、(曲の中身が非常に能狂言の世界的なので)能狂言の先生の教えを乞われたことがありまして。
その時のお話では、日本語の発音発声は、室町時代以前と以後くらいで大きな変化があったのではないか、との事。(そう言えば、英語にも大母音推移、とかいうのがあったらしい。昔の英語発音は、今のものとは、てんで違って聞こえるらしいです)
平安から室町くらいは、
端的に言えば、能狂言で使われているような、口腔の奥の方で響かせる感じの発声をしていたらしいです。
それが、江戸に入ってからは、いわゆる江戸っ子言葉の
「江戸っ子だってねぇ、寿司食いねぇ」的なアップテンポで、口腔の比較的前の方で発音する発声に変わっていったんですって。
政治の中心が関西から関東へ移っていった、というのも関係してるのかなぁ。
で、ともかく、現代語になると、ほとんど口腔の奥の方で発音することは日常的にありません。キビキビした感じで良いのですが、そうなると、母音のうちでも「イ」とか「エ」は、唇を左右に引いて、ちょっと平べったいサウンドを使って表現するようになった。
これが、歌う時、大きな障害! 男声ではあまり感じないんですが、女声では、「イ」と「エ」が出てきた瞬間に、現代日本語発音の平べったい音になりやすい。
女性の方が日常的に
「えーっ!」とか、
「いいー!」とか、
叫ぶからだろうか。
※そー言えば、「あ」も難しい。
東日本復興ソングの「花はさく」の聞かせどころの「はな~は は~なは はなはさく」の「な」だけ、なんか平べったくベトーっとした音が鳴っちゃって台無しになりやすい。音形のせいかしらん。ドイツの少年合唱団と一緒に歌った時、彼らはha-na-wa ha-na-wa ha-na-wa-sa-kuで発音してて、そりゃあきれいな「な」でございました。ちゃんとNの口をしてから、Aの母音に入るので、美しいのだなー。
室町くらいの深い響きの母音は、どーいう感じか?
というと、野村萬斎さんのセリフ回しを思い出していただけばよい。
「これはこのあたりの者でござる。やいやい、太郎冠者、あるか」みたいなヤツです。
南京玉すだれの口上とかも、いいかもしんない~(≧▽≦)
能狂言の、口腔の深いところで響かせる倍音は、実はドイツリート的なのかもしれませんねー。
というわけで、
現代日本語の達人である
現代人の私たちは、
つい日常の言語感覚で
日本語の曲を歌ってしまい、
ドツボにハマるのであります。
現代語発音も、うまく使えば、いい感じ~(≧▽≦)で使えるところもたくさんあるので、最近マエストロは、従来の基本音型3つの使い分けに、この古語風(リアrear)と現代風(フロントfront)も加えてチェンジするように指導されてます。ほとんど車のシフトチェンジ状態~(≧▽≦)。
※この間なんか、廣瀬量平の『海鳥の詩』で「ゆくえ」というのを古語風に、
「ゆくゑ」(発音はiyu-ku-weで、ご丁寧にもkは撥音ではなく、鼻濁音的)で考えるといい、と教えて下さり、なるほど、その方がここではハマる! と喜んでメモしてしまった。
だいたいにおいて、譜面に、コレコレのことを(自分に分かる形でいいんですが)書いておけ、という指示がたくさん入ります。特有の用語がたくさんあって、それをきっちり書いておかないと、置いてかれてしまう。
みんなの共通認識で、用語を決めておくと、効率的に短時間で曲が整う、というのがマエストロの持論なんでありますが、確かにこの方法、便利なんです。
基本音型3つについては、また改めて書いてみたいと思いますが、フロントだ、リアだ、と一言譜面に書いておくだけで、要求される音に入ろう、という態勢が出来ますから、ラクチンです。
「出来る、出来ないは別として、まずやろうとすることが大事なんです」
↑
出来ない群れである私たちを、叱咤激励して下さるマエストロの口癖でござる。
●第九と言っても、別に演奏会じゃない
単なる練習会なんですが、
磐田バッハ企画で、
久しぶりにBeethovenの第九も
歌ってみようじゃないか、の会。
で、もちろんバロック唱法でやる。
第九は昔、死ぬほどやったんで暗譜してあるが、
バロック唱法でやるの、初めて。
バロックでやるなら、A=415Hzで、キーボード伴奏かぁ、それなら低くて楽でいいや~o(^-^)oワクワク
とか思っていたら、
ピアノがあるから、
ピアノ伴奏だなっ!
に決定。ううう、A=440Hz(ToT)
何が辛いって、
A=440でG(ハ長調で読むとソ)を連呼するとこ。
それより高いA(ラ)とかB(シ♭)とか
H(シ)は、一瞬のチカラワザで、
何とかなっちゃう。もっとも、全ての音をベストポジションキープで鳴らすのは難しいんだけどね。
ともかく、Gが意外と辛い。多分ポジションチェンジど真ん中の高さなんで、良い状態を保つのが難しいところなんだと思う。一発芸で1音だけなら、気合いで何とかなるものだけど、いくつもあると、全てを同じ高さ、同じ発声でやり続けるのは大変。
ちなみに、ご丁寧にも、6個連続である。絶叫状態である。この音が下がると、ひっじょーにお聞き苦しい。
もう一つ、Aの超ロングトーンも非道。9小節くらい伸ばしてから、また連呼が4回くらいある。オニ。
Beethovenの時代は、現代のチューニングより低く、バロックに近かったようなんですが、それを現代の楽器のチューニングに合わせてやると、とてつもないことになってしまう。
第九は日本全国でよく
演奏される曲ですが、
どこでも、上が高すぎて、
みんな苦労している。
普段はソプラノをやってる人が、「出ないっ!」てんで、
大挙してアルトになだれ込んだりするもんだから、アルトが異様に多い編成になっちゃったりする。ありがち。
無論、他のパートも高めなんで、実はそれぞれ苦労している。バスなんか、こんな高いとこは、テナーに歌ってもらえばいいじゃん!
という、これまた殺人的なとこがあり、譜面を見ると、バスなのに、五線の上の音だらけ。こっちもやっぱり、絶叫系………か?
まぁ、男声だけでやるカッコイい行進曲のとこもあるから、他で絶叫してもいいか。(いいのか?!)
一カ所だけ、バリトンソロ
に先導されて、男声だけでやる箇所がありまして、
男声の人々は、ここが
大好きで、第九を歌い
に来るんじゃないか?
というメンバーもいたりする。
昨日ここの箇所で、
うちのマエストロが、
「ここは、“行け行け、ドンドン”のとこですから」
とおっしゃってて、
1人で大うけして、
心の中でこっそり
「♪こいけ屋~、ポテトチ~ップス!」
と、歌ってしまいました。
マエストロのお心の中でも、
このCMソングが流れていたに違いない。
で、まあ、全曲通しました。
が、肝心の男声が、この日は
なんと「第九って、初めてなんですよ~」のユビラーテのM島さんしかいない。
磐田メンバーのテナーIヶ谷さんとバスのY内さんは揃って欠席。
Y内さんの勤続30周年リフレッシュ休暇旅行(にIヶ谷さんも誘われて)で、2人でスペインにとんずらしてしまっていたのであった!
Facebookに、「今ここ」情報と美しい写真の数々がアップされ、ひたすら指をくわえていた。(グラナダとかコルドバとかは、昔、父と短大時代に行ったので懐かしく見ていたのだが)バルセロナやら、モンセラット(くそー、うらやましいゾ!)やらまで行ってて、どんだけ強行軍なんだか………(^◇^;)と、お二人の体調が心配な今日この頃なのであった。
てなわけで、第九を歌おう会の日は、男声ほぼ無し。んなもんだから、バリトンソロのとこも、男声の「いけいけドンドン」も、女声のみんなでてきとーに歌ってしまう、というパターン(磐田では、ありがち)。
さらに、第九って、ソリスト4人が合唱するところもあるんだが、ここも、みんなでてきとーに歌ってしまう、と。
結局、普段歌わないとこまで、フルに歌いまくりをして、終わってみたら、ヘトヘト状態に~( ̄。 ̄;)
で、また刀削麺を食べました~(≧▽≦)

●翌日は、東京にたどり着き、またしてもしごきを受ける、と。
冒頭タイトルの「信長制覇」というのは、この日練習した曲の話でございます。
決してゲーム「信長の野望」とかにハマった、というのではありません。
合唱やってる人でないと、
「信長」と言っても
「織田信長か?」になっちゃうんだけど、
作曲家で信長貴富(のぶながたかとみ)さんとおっしゃるステキな曲を作る方がいらっしゃるのです。今回の東京練習は、クラブOB会合唱団ソーニョで、この信長さんの「くちびるに歌を」に挑戦、という話だったのです。
↑
※以上、合唱人以外の方向けのフォローである。一応、気を使ってフォローしてみました~(が、たいてい話題がディープな合唱オタクの世界なんで、たまにフォローしてみてもしょーがないよーな気もするのだが)
●年を取ると、足が上がらなくなる!
というお話が指揮者さまからあり、みんなで大うけしてたのですが。
最近会社で、現場用に配布された安全シューズが、つま先が上に反っていて、
ちょっとした段差などで足が上がりやすいように工夫されているのだそうです。
で、この靴の型番が、
G3。
「ジーサン」……………( ̄。 ̄;)
う、うーむ。
狙ったかのよーな、
絶妙の型番。
なんで、そんな話になったのか? というと、狙った音程にピタッと足が上がらないっつーか、声がはまらないところがあって、
若い頃なら、何も考えなくても、軽々こなせたことが、
年を取ると次第に何気にはできなくなってくるのだ、という話。
なもんだから、十分意識して、しっかり準備してからでないと、狙った場所に到達できない、と自覚し、ちゃんと前もって準備してネ………
といった趣旨のお話だったトです。
でも、つい、「ジーサン」でウケていて、肝心のお話が心に染みていないような(^◇^;)
ご指摘のあった箇所は、
信長さんのじゃなくて、
MiskinisのAve Mariaの冒頭ソプラノ部分。
E-majorで、
H-H-H H-A-G♯-A-F♯-G♯
と動くメインテーマ部分。
H-A-G♯の部分が、
イー加減に、
「このへんだろう」で
動いちゃってて、だだだ~、と雪崩落ちちゃうもんだから、G♯にちゃんと着地出来ていない。リズムがちょっと現代風であることも災いして、
みんなそれぞれ、違うリズム感と違う音程感で、ここらへんだろ~、だだだ~………と。
困ったことに、この
メロディー、メインテーマなもんだから、何回も出てくる。
で、何回でも、おんなじよーに、失敗する。
なもんで、見かねて
「ジーサン」の話が出たわけで。
●やっぱ、スケール練習だわ!
こういった、野生のカンに任せて、「た、多分、このへんだよね」でやっちゃうの、
実はほとんどどこの合唱団でもありがちな話でして。
研ぎ澄まされた野生のカンならいいんだけど、
よくわかんないから、このへん………的なカンで動くので、
何度挑戦しても、あえなく撃沈する、というパターンが多い。
観察すると、みんなが苦手なのは、半音階進行とか、4度跳躍とか、決まっている。
こーゆーところは、少しトレーニングを積まないと、自然発生的には克服できない箇所。
毎回おんなじところで引っかかって停滞する。
うーむ、これって、
小さい子のピアノ発表会と同じなんでは?(^◇^;)
弾けるところは、超高速で弾くんだけど、弾けない箇所に入ると、途端にたどたど。挙げ句の果てに止まっちゃって、頭が真っ白になって、半泣き………という、アレに非常に近いよーな気がする。
私も苦手な音程はあるので、人のことは言えないのだが、
苦手なところは、そこだけピックアップしてアタックして出来るようにする、という取り出しトレーニングをすると、早く克服できるような気がします。
後は、日常的に、
半音階スケールの練習。
うちのマエストロに言わせると、こういう音程感覚に問題のある箇所は、
「メロディーだと思ってやるからいけない。むしろ、スケールの中の1音だ、と思って、スケールを徹底的に練習した方が早い」
とのこと。ナルホド、その方が効率的だ、と思って、最近はもっぱらスケール練習にいそしんで、いろんな難しい音程をクリアするように頑張っています。
スケールの中の音として見直してみると、例えばモツレクの第2曲目のKyrie、最後の
Kyrie eleisonのソプラノが、
D-D-C♯-D-D-C♯-D
と、スケールで見れば、
ごく単純な動きなのに、
これがてんで出来ない。
C♯へ動くのが、
まず、「ええい、このへんだろう!」で、イー加減なとこに行くので、いざ、Dに戻ろうとしても、正確なDに戻れていない。
さらに、もう1回C♯に行って、もう1回Dに落ち着け、という形なんだけど、既にそこに至るまでの道程がイー加減なもんだから、落ち着こうにも、落ち着けない。私はどこ? ヘンなのは分かるけど、どーヘンなのかわかんないー!……。
結果として、ひっじょーに気持ちの悪い音程で、皆、あがいてしまう………というのが、どこでもありがち!
やはり、半音刻みで、スケール内の音は、それぞれここだ! というのを自主練で見つけていかないとアカン!
てなわけで、東京練習では、
またしてもしごき倒されたわけでございました。
信長制覇………まだ道、遠し……かもしんない~(ToT)
我らの指揮者さまが、
いかに素晴らしく振って下さっても、1人1人が
「こんなもんかなー。よくわかんないー」では、なかなか
指揮者さまの表現したい音楽に追いついていけませんからね。み
んなで頑張ってスケール練習しましょうよー!
そして、次回の練習では、
「おおっ!」と目を見張らせるのだ。ガンバンベー!
●オマケ写真

浅草のバーガーキングで一休みしてたら、

目の前の神谷バーの角を
はとバスが。
さらに、その後、何のパレードか
わからなかったが、鼓笛隊みたいのが。暑かったろうなー。
単なる練習会なんですが、
磐田バッハ企画で、
久しぶりにBeethovenの第九も
歌ってみようじゃないか、の会。
で、もちろんバロック唱法でやる。
第九は昔、死ぬほどやったんで暗譜してあるが、
バロック唱法でやるの、初めて。
バロックでやるなら、A=415Hzで、キーボード伴奏かぁ、それなら低くて楽でいいや~o(^-^)oワクワク
とか思っていたら、
ピアノがあるから、
ピアノ伴奏だなっ!
に決定。ううう、A=440Hz(ToT)
何が辛いって、
A=440でG(ハ長調で読むとソ)を連呼するとこ。
それより高いA(ラ)とかB(シ♭)とか
H(シ)は、一瞬のチカラワザで、
何とかなっちゃう。もっとも、全ての音をベストポジションキープで鳴らすのは難しいんだけどね。
ともかく、Gが意外と辛い。多分ポジションチェンジど真ん中の高さなんで、良い状態を保つのが難しいところなんだと思う。一発芸で1音だけなら、気合いで何とかなるものだけど、いくつもあると、全てを同じ高さ、同じ発声でやり続けるのは大変。
ちなみに、ご丁寧にも、6個連続である。絶叫状態である。この音が下がると、ひっじょーにお聞き苦しい。
もう一つ、Aの超ロングトーンも非道。9小節くらい伸ばしてから、また連呼が4回くらいある。オニ。
Beethovenの時代は、現代のチューニングより低く、バロックに近かったようなんですが、それを現代の楽器のチューニングに合わせてやると、とてつもないことになってしまう。
第九は日本全国でよく
演奏される曲ですが、
どこでも、上が高すぎて、
みんな苦労している。
普段はソプラノをやってる人が、「出ないっ!」てんで、
大挙してアルトになだれ込んだりするもんだから、アルトが異様に多い編成になっちゃったりする。ありがち。
無論、他のパートも高めなんで、実はそれぞれ苦労している。バスなんか、こんな高いとこは、テナーに歌ってもらえばいいじゃん!
という、これまた殺人的なとこがあり、譜面を見ると、バスなのに、五線の上の音だらけ。こっちもやっぱり、絶叫系………か?
まぁ、男声だけでやるカッコイい行進曲のとこもあるから、他で絶叫してもいいか。(いいのか?!)
一カ所だけ、バリトンソロ
に先導されて、男声だけでやる箇所がありまして、
男声の人々は、ここが
大好きで、第九を歌い
に来るんじゃないか?
というメンバーもいたりする。
昨日ここの箇所で、
うちのマエストロが、
「ここは、“行け行け、ドンドン”のとこですから」
とおっしゃってて、
1人で大うけして、
心の中でこっそり
「♪こいけ屋~、ポテトチ~ップス!」
と、歌ってしまいました。
マエストロのお心の中でも、
このCMソングが流れていたに違いない。
で、まあ、全曲通しました。
が、肝心の男声が、この日は
なんと「第九って、初めてなんですよ~」のユビラーテのM島さんしかいない。
磐田メンバーのテナーIヶ谷さんとバスのY内さんは揃って欠席。
Y内さんの勤続30周年リフレッシュ休暇旅行(にIヶ谷さんも誘われて)で、2人でスペインにとんずらしてしまっていたのであった!
Facebookに、「今ここ」情報と美しい写真の数々がアップされ、ひたすら指をくわえていた。(グラナダとかコルドバとかは、昔、父と短大時代に行ったので懐かしく見ていたのだが)バルセロナやら、モンセラット(くそー、うらやましいゾ!)やらまで行ってて、どんだけ強行軍なんだか………(^◇^;)と、お二人の体調が心配な今日この頃なのであった。
てなわけで、第九を歌おう会の日は、男声ほぼ無し。んなもんだから、バリトンソロのとこも、男声の「いけいけドンドン」も、女声のみんなでてきとーに歌ってしまう、というパターン(磐田では、ありがち)。
さらに、第九って、ソリスト4人が合唱するところもあるんだが、ここも、みんなでてきとーに歌ってしまう、と。
結局、普段歌わないとこまで、フルに歌いまくりをして、終わってみたら、ヘトヘト状態に~( ̄。 ̄;)
で、また刀削麺を食べました~(≧▽≦)
●翌日は、東京にたどり着き、またしてもしごきを受ける、と。
冒頭タイトルの「信長制覇」というのは、この日練習した曲の話でございます。
決してゲーム「信長の野望」とかにハマった、というのではありません。
合唱やってる人でないと、
「信長」と言っても
「織田信長か?」になっちゃうんだけど、
作曲家で信長貴富(のぶながたかとみ)さんとおっしゃるステキな曲を作る方がいらっしゃるのです。今回の東京練習は、クラブOB会合唱団ソーニョで、この信長さんの「くちびるに歌を」に挑戦、という話だったのです。
↑
※以上、合唱人以外の方向けのフォローである。一応、気を使ってフォローしてみました~(が、たいてい話題がディープな合唱オタクの世界なんで、たまにフォローしてみてもしょーがないよーな気もするのだが)
●年を取ると、足が上がらなくなる!
というお話が指揮者さまからあり、みんなで大うけしてたのですが。
最近会社で、現場用に配布された安全シューズが、つま先が上に反っていて、
ちょっとした段差などで足が上がりやすいように工夫されているのだそうです。
で、この靴の型番が、
G3。
「ジーサン」……………( ̄。 ̄;)
う、うーむ。
狙ったかのよーな、
絶妙の型番。
なんで、そんな話になったのか? というと、狙った音程にピタッと足が上がらないっつーか、声がはまらないところがあって、
若い頃なら、何も考えなくても、軽々こなせたことが、
年を取ると次第に何気にはできなくなってくるのだ、という話。
なもんだから、十分意識して、しっかり準備してからでないと、狙った場所に到達できない、と自覚し、ちゃんと前もって準備してネ………
といった趣旨のお話だったトです。
でも、つい、「ジーサン」でウケていて、肝心のお話が心に染みていないような(^◇^;)
ご指摘のあった箇所は、
信長さんのじゃなくて、
MiskinisのAve Mariaの冒頭ソプラノ部分。
E-majorで、
H-H-H H-A-G♯-A-F♯-G♯
と動くメインテーマ部分。
H-A-G♯の部分が、
イー加減に、
「このへんだろう」で
動いちゃってて、だだだ~、と雪崩落ちちゃうもんだから、G♯にちゃんと着地出来ていない。リズムがちょっと現代風であることも災いして、
みんなそれぞれ、違うリズム感と違う音程感で、ここらへんだろ~、だだだ~………と。
困ったことに、この
メロディー、メインテーマなもんだから、何回も出てくる。
で、何回でも、おんなじよーに、失敗する。
なもんで、見かねて
「ジーサン」の話が出たわけで。
●やっぱ、スケール練習だわ!
こういった、野生のカンに任せて、「た、多分、このへんだよね」でやっちゃうの、
実はほとんどどこの合唱団でもありがちな話でして。
研ぎ澄まされた野生のカンならいいんだけど、
よくわかんないから、このへん………的なカンで動くので、
何度挑戦しても、あえなく撃沈する、というパターンが多い。
観察すると、みんなが苦手なのは、半音階進行とか、4度跳躍とか、決まっている。
こーゆーところは、少しトレーニングを積まないと、自然発生的には克服できない箇所。
毎回おんなじところで引っかかって停滞する。
うーむ、これって、
小さい子のピアノ発表会と同じなんでは?(^◇^;)
弾けるところは、超高速で弾くんだけど、弾けない箇所に入ると、途端にたどたど。挙げ句の果てに止まっちゃって、頭が真っ白になって、半泣き………という、アレに非常に近いよーな気がする。
私も苦手な音程はあるので、人のことは言えないのだが、
苦手なところは、そこだけピックアップしてアタックして出来るようにする、という取り出しトレーニングをすると、早く克服できるような気がします。
後は、日常的に、
半音階スケールの練習。
うちのマエストロに言わせると、こういう音程感覚に問題のある箇所は、
「メロディーだと思ってやるからいけない。むしろ、スケールの中の1音だ、と思って、スケールを徹底的に練習した方が早い」
とのこと。ナルホド、その方が効率的だ、と思って、最近はもっぱらスケール練習にいそしんで、いろんな難しい音程をクリアするように頑張っています。
スケールの中の音として見直してみると、例えばモツレクの第2曲目のKyrie、最後の
Kyrie eleisonのソプラノが、
D-D-C♯-D-D-C♯-D
と、スケールで見れば、
ごく単純な動きなのに、
これがてんで出来ない。
C♯へ動くのが、
まず、「ええい、このへんだろう!」で、イー加減なとこに行くので、いざ、Dに戻ろうとしても、正確なDに戻れていない。
さらに、もう1回C♯に行って、もう1回Dに落ち着け、という形なんだけど、既にそこに至るまでの道程がイー加減なもんだから、落ち着こうにも、落ち着けない。私はどこ? ヘンなのは分かるけど、どーヘンなのかわかんないー!……。
結果として、ひっじょーに気持ちの悪い音程で、皆、あがいてしまう………というのが、どこでもありがち!
やはり、半音刻みで、スケール内の音は、それぞれここだ! というのを自主練で見つけていかないとアカン!
てなわけで、東京練習では、
またしてもしごき倒されたわけでございました。
信長制覇………まだ道、遠し……かもしんない~(ToT)
我らの指揮者さまが、
いかに素晴らしく振って下さっても、1人1人が
「こんなもんかなー。よくわかんないー」では、なかなか
指揮者さまの表現したい音楽に追いついていけませんからね。み
んなで頑張ってスケール練習しましょうよー!
そして、次回の練習では、
「おおっ!」と目を見張らせるのだ。ガンバンベー!
●オマケ写真
浅草のバーガーキングで一休みしてたら、
目の前の神谷バーの角を
はとバスが。
さらに、その後、何のパレードか
わからなかったが、鼓笛隊みたいのが。暑かったろうなー。
●昨日は磐田でブラームス漬け!
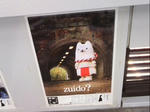
↑
磐田ゆるキャラ・しっぺいくんのポスター。観光案内で明治の隧道。駅前の観光案内所でクリアファイルをゲットしてきました(≧▽≦)
来年2月のオール・ブラームス演奏会に向けて、磐田ではブラームスしごきが始まっているんですが、
昨日はOp.92の「4つの歌」の音取りを、サクサクサク~、と全曲通し。
1番の「O shone Nacht」(例によってウムラウト無視、でお送りしてます)は、大昔(と言っても2006年だったんで、8年前)にジョイオブでちょろっとやり、撃沈したヤツで、
2番の「Spatherbst」(再びウムラウト無視)は、聴いたことあるけど、やったことない。
3番の「Abendlied」は、なんとなく見たことがある………かな?
4番の「Warum?」は、昔、譜面をチラ見して、「無理!」とはだしで逃げ出したような記憶が(^◇^;)
↑
4番の歌詞、ゲーテだったんですねー。ちっとも気がつきませんでしたー。
相変わらず、いい加減~♪
家で一応、軽くアルトの音だけは見ておいたんですけど、
磐田に行ったら、最初ソプラノが1人もいなくて(後からO根さんとN本さんが来てくれたんで、ものすご、ほぉー)、
例によって、「あ~、とりあえずソプラノ、やっといて」になった!
ううう、ブラームスは
ソプラノはかなり高い跳躍が多いので、内心またしても
ムンクしながら、何とかやりましたー。
なんか、なし崩しにソプラノに戻ることになりそうだなー。まぁ、両方練習すると、両方とも楽しいんで、いいんですけどもさ。

↑
お宅に飾ってあった一輪挿し。
こうするとドクダミも可憐。
●ブラームスは苦手だったんだよねー
N村先生のとこで歌曲の練習しても、ブラームスとかヴォルフとかになると、なんかフレージングが長くって、なかなか保てないもんだから、むじゅかしい、苦手~(ToT)
で泣いてたものなんですが、
バロック唱法で毎週毎週
しごかれているうちに、
何でかよくわかんないんだけど、ブラームスもコワくなくなってきました。
バッハの時代に近い
モーツァルトの歌曲も、
昔は挑戦しては撃沈ばかりだったのが、あんまりコワくなくなってきました。
2月にガマさんとモーツァルトをデュエットした時も、昔ほど苦労はしなかったんですが、(とは言え、なかなかこうだ、というのに仕上げるには、まだ道遠し、の感はありますが)
静岡でU田さんとH部さんに付き合ってもらって、大分時間を割いてもらったおかげで、ともかく止まらずに最後までは歌えるようになり、ヤレヤレ。
↑
せっかく練習したんで、もったいないからジョイオブでやっちゃおうか、という話になりました。
「暗譜できないー」とU田さんから泣きが入っているので、
(右に同じなのだが!)
「譜持ちでいいっしょー(^◇^;)」とか言ってますが。
↑
とか言いながら、結構
頑張って暗譜してきたりするもんなー。私も頑張って暗譜に挑戦した方がいいのかにゃー。覚えられるかにゃー。(再び、いい加減)
●通奏低音が沖縄ペンタ……なのか?
で、「4つの歌」の話に戻りますが、3曲目の「Abendlied夕べの歌」の譜面を見ていたら、
隣でN本さんが、
「このバス、沖縄民謡みたい………」
とボソッと。
で、「ウッソー」とか言いながら見たら、ピアノ前奏の左手の通奏低音っぽいとこと、バスの音形が、た、たしかに
それっぽい。
ブラームスは、沖縄ペンタトニックをひそかに使っていた
のか?! ひそかに琉球王国に行ってたのか?!
で思わず吹きそうになっちゃったんですけど。
よくよく見てみたら、
沖縄ペンタ(ニロ抜き長音階と一緒)というよりは、
ヨナ抜き長音階みたいな作りでございました~♪
大変ロマンチックな曲なのに、頭の中でうっかり
「ハイサイおじさん♪」とか流れちゃって、アワワでしたぁ。
もおぉ、N本さんたら、
なにげにお茶目なんだからー。
でも、この曲、すごくおもしろい作りですねぇ。
3小節目から13小節目までが主要テーマなんだけど、よく見ると調号はF-durの♭1個で書いてるのに、臨時記号で♯が出まくり!
「augumentedしてるから、見てご覧なさい」
と先生に言われて、
「ああっ! そう言われてみれば、♭系の調なのに、♯だらけー!」
と、初めて気づく、と。
えへへ、てんでアナリゼ、
出来てまへーん。
ブラームスくらい新しい時代になってくると、7th chordがたくさん出てきて、なんていうのか、ビミョーな色合いの、ニュアンスに富んだ和音が多用されていて、拾っていくと、とっても楽しい。昨夜も、ドイツレクイエムやらこの曲集やら弾いて楽しんでしまった。
27小節の和音も、C(ハ長調のドの上に積み重なった和音として捕らえる)の和音なんだけど、普通のドミソとは見た目からして違う。
バスがⅠ度の音、ソプラノがⅢ度の音(※普通のドミソの和音などでは、ドミソは、Ⅰ度ーⅢ度ーⅤ度と読みます)、で、そこまでは普通なんだけど、
数えてみたら、
テナーは♭7thで、
アルトは♭9thでしたぁ!
キャーッ♡
ジャズコードみたい~♪
調子に乗って、他のところも、ジャズコードで見てみたら、それっぽいものが満載。
そうかぁ、
こーいう楽しみ方もあるかぁ。
休憩時間に先生に
そんなお話をしていたら、
私がジャズを習ったことが
あるのをご存じのマエストロ、
「各和音に、ジャズのコードネームを書いておくと便利なんですよー」
とニコニコ。
う、うーむ、さすが。
こだわりがないというか、
使えるものは有効に使おう、というか、
何とも闊達自在な精神の持ち主でいらっしゃいます。
●ちなみに
ヨナ抜きとかニロ抜きとか、
ペンタとか、今回いろいろ出てきてますが、
要は伝統音楽、民謡で使われる5音で構成される音階(これをペンタトニックという)の話です。
西洋音楽では、普通はドレミファソラシドの7音を使ってるけど、世界中あちこちで、一番伝統的で、誰もが和むのが5音の世界。
ヨナ抜きは、「4度と7度」が抜けてるヤツで、
ドレミファソラシドじゃなくて、
ドレミソラドになる。
ニロ抜きは、「2度と6度」が抜けてて、
ドレミファソラシドじゃなくて、
ドミファソシドになる。
文部省唱歌は、西洋音楽風のものが多いですが、同じく5音スケールが多いスコットランド民謡を採用したものも多いので、意外とヨナ抜きになっているそうです。
日本人はヨナ抜きが大好きなんで、実は民謡以外でも、
演歌でもポップスでも、
ヨナ抜きがヒットするんだとか。
「上を向いて歩こう」が
ヨナ抜きなのは知ってたんですが、
なんと、
「リンゴ追分」から
「箱根八里の半次郎」、
「昴」「木綿のハンカチーフ」「夏祭り」「恋するフォーチュンクッキー」まで、
みんなヨナ抜きなのでした!
ビックリ!
ちなみに、ニロ抜き長音階というのが、沖縄ペンタトニックでして、どんなんや?
と思われた方は、
THE BOOMの「島唄」を
思い出してみてください。
あれ、です。
ブラームスの歌曲も、
島唄も、フォーチュンクッキーも、根っこはみんな
同じなのかもしれないー!
楽しいっ!
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
↑
磐田ゆるキャラ・しっぺいくんのポスター。観光案内で明治の隧道。駅前の観光案内所でクリアファイルをゲットしてきました(≧▽≦)
来年2月のオール・ブラームス演奏会に向けて、磐田ではブラームスしごきが始まっているんですが、
昨日はOp.92の「4つの歌」の音取りを、サクサクサク~、と全曲通し。
1番の「O shone Nacht」(例によってウムラウト無視、でお送りしてます)は、大昔(と言っても2006年だったんで、8年前)にジョイオブでちょろっとやり、撃沈したヤツで、
2番の「Spatherbst」(再びウムラウト無視)は、聴いたことあるけど、やったことない。
3番の「Abendlied」は、なんとなく見たことがある………かな?
4番の「Warum?」は、昔、譜面をチラ見して、「無理!」とはだしで逃げ出したような記憶が(^◇^;)
↑
4番の歌詞、ゲーテだったんですねー。ちっとも気がつきませんでしたー。
相変わらず、いい加減~♪
家で一応、軽くアルトの音だけは見ておいたんですけど、
磐田に行ったら、最初ソプラノが1人もいなくて(後からO根さんとN本さんが来てくれたんで、ものすご、ほぉー)、
例によって、「あ~、とりあえずソプラノ、やっといて」になった!
ううう、ブラームスは
ソプラノはかなり高い跳躍が多いので、内心またしても
ムンクしながら、何とかやりましたー。
なんか、なし崩しにソプラノに戻ることになりそうだなー。まぁ、両方練習すると、両方とも楽しいんで、いいんですけどもさ。
↑
お宅に飾ってあった一輪挿し。
こうするとドクダミも可憐。
●ブラームスは苦手だったんだよねー
N村先生のとこで歌曲の練習しても、ブラームスとかヴォルフとかになると、なんかフレージングが長くって、なかなか保てないもんだから、むじゅかしい、苦手~(ToT)
で泣いてたものなんですが、
バロック唱法で毎週毎週
しごかれているうちに、
何でかよくわかんないんだけど、ブラームスもコワくなくなってきました。
バッハの時代に近い
モーツァルトの歌曲も、
昔は挑戦しては撃沈ばかりだったのが、あんまりコワくなくなってきました。
2月にガマさんとモーツァルトをデュエットした時も、昔ほど苦労はしなかったんですが、(とは言え、なかなかこうだ、というのに仕上げるには、まだ道遠し、の感はありますが)
静岡でU田さんとH部さんに付き合ってもらって、大分時間を割いてもらったおかげで、ともかく止まらずに最後までは歌えるようになり、ヤレヤレ。
↑
せっかく練習したんで、もったいないからジョイオブでやっちゃおうか、という話になりました。
「暗譜できないー」とU田さんから泣きが入っているので、
(右に同じなのだが!)
「譜持ちでいいっしょー(^◇^;)」とか言ってますが。
↑
とか言いながら、結構
頑張って暗譜してきたりするもんなー。私も頑張って暗譜に挑戦した方がいいのかにゃー。覚えられるかにゃー。(再び、いい加減)
●通奏低音が沖縄ペンタ……なのか?
で、「4つの歌」の話に戻りますが、3曲目の「Abendlied夕べの歌」の譜面を見ていたら、
隣でN本さんが、
「このバス、沖縄民謡みたい………」
とボソッと。
で、「ウッソー」とか言いながら見たら、ピアノ前奏の左手の通奏低音っぽいとこと、バスの音形が、た、たしかに
それっぽい。
ブラームスは、沖縄ペンタトニックをひそかに使っていた
のか?! ひそかに琉球王国に行ってたのか?!
で思わず吹きそうになっちゃったんですけど。
よくよく見てみたら、
沖縄ペンタ(ニロ抜き長音階と一緒)というよりは、
ヨナ抜き長音階みたいな作りでございました~♪
大変ロマンチックな曲なのに、頭の中でうっかり
「ハイサイおじさん♪」とか流れちゃって、アワワでしたぁ。
もおぉ、N本さんたら、
なにげにお茶目なんだからー。
でも、この曲、すごくおもしろい作りですねぇ。
3小節目から13小節目までが主要テーマなんだけど、よく見ると調号はF-durの♭1個で書いてるのに、臨時記号で♯が出まくり!
「augumentedしてるから、見てご覧なさい」
と先生に言われて、
「ああっ! そう言われてみれば、♭系の調なのに、♯だらけー!」
と、初めて気づく、と。
えへへ、てんでアナリゼ、
出来てまへーん。
ブラームスくらい新しい時代になってくると、7th chordがたくさん出てきて、なんていうのか、ビミョーな色合いの、ニュアンスに富んだ和音が多用されていて、拾っていくと、とっても楽しい。昨夜も、ドイツレクイエムやらこの曲集やら弾いて楽しんでしまった。
27小節の和音も、C(ハ長調のドの上に積み重なった和音として捕らえる)の和音なんだけど、普通のドミソとは見た目からして違う。
バスがⅠ度の音、ソプラノがⅢ度の音(※普通のドミソの和音などでは、ドミソは、Ⅰ度ーⅢ度ーⅤ度と読みます)、で、そこまでは普通なんだけど、
数えてみたら、
テナーは♭7thで、
アルトは♭9thでしたぁ!
キャーッ♡
ジャズコードみたい~♪
調子に乗って、他のところも、ジャズコードで見てみたら、それっぽいものが満載。
そうかぁ、
こーいう楽しみ方もあるかぁ。
休憩時間に先生に
そんなお話をしていたら、
私がジャズを習ったことが
あるのをご存じのマエストロ、
「各和音に、ジャズのコードネームを書いておくと便利なんですよー」
とニコニコ。
う、うーむ、さすが。
こだわりがないというか、
使えるものは有効に使おう、というか、
何とも闊達自在な精神の持ち主でいらっしゃいます。
●ちなみに
ヨナ抜きとかニロ抜きとか、
ペンタとか、今回いろいろ出てきてますが、
要は伝統音楽、民謡で使われる5音で構成される音階(これをペンタトニックという)の話です。
西洋音楽では、普通はドレミファソラシドの7音を使ってるけど、世界中あちこちで、一番伝統的で、誰もが和むのが5音の世界。
ヨナ抜きは、「4度と7度」が抜けてるヤツで、
ドレミファソラシドじゃなくて、
ドレミソラドになる。
ニロ抜きは、「2度と6度」が抜けてて、
ドレミファソラシドじゃなくて、
ドミファソシドになる。
文部省唱歌は、西洋音楽風のものが多いですが、同じく5音スケールが多いスコットランド民謡を採用したものも多いので、意外とヨナ抜きになっているそうです。
日本人はヨナ抜きが大好きなんで、実は民謡以外でも、
演歌でもポップスでも、
ヨナ抜きがヒットするんだとか。
「上を向いて歩こう」が
ヨナ抜きなのは知ってたんですが、
なんと、
「リンゴ追分」から
「箱根八里の半次郎」、
「昴」「木綿のハンカチーフ」「夏祭り」「恋するフォーチュンクッキー」まで、
みんなヨナ抜きなのでした!
ビックリ!
ちなみに、ニロ抜き長音階というのが、沖縄ペンタトニックでして、どんなんや?
と思われた方は、
THE BOOMの「島唄」を
思い出してみてください。
あれ、です。
ブラームスの歌曲も、
島唄も、フォーチュンクッキーも、根っこはみんな
同じなのかもしれないー!
楽しいっ!
(≧▽≦)(≧▽≦)(≧▽≦)
カレンダー
カテゴリー
フリーエリア
最新コメント
[12/10 Meamo]
[09/15 スーパーコピーブランド激安通販専門店]
[09/04 p9nu9tw180]
[09/02 t5mn6rt387]
[09/01 b6ck4kz060]
最新記事
(12/07)
(08/06)
(07/28)
(07/09)
(07/09)
最新トラックバック
プロフィール
HN:
No Name Ninja
性別:
非公開
ブログ内検索
最古記事
P R
